物語の再構築
- yamashina shigeru
- 2025年8月11日
- 読了時間: 4分
「人生をかけて追求する問い」を見つける究極の思考基盤
Calling
垂水隆幸 著
読了
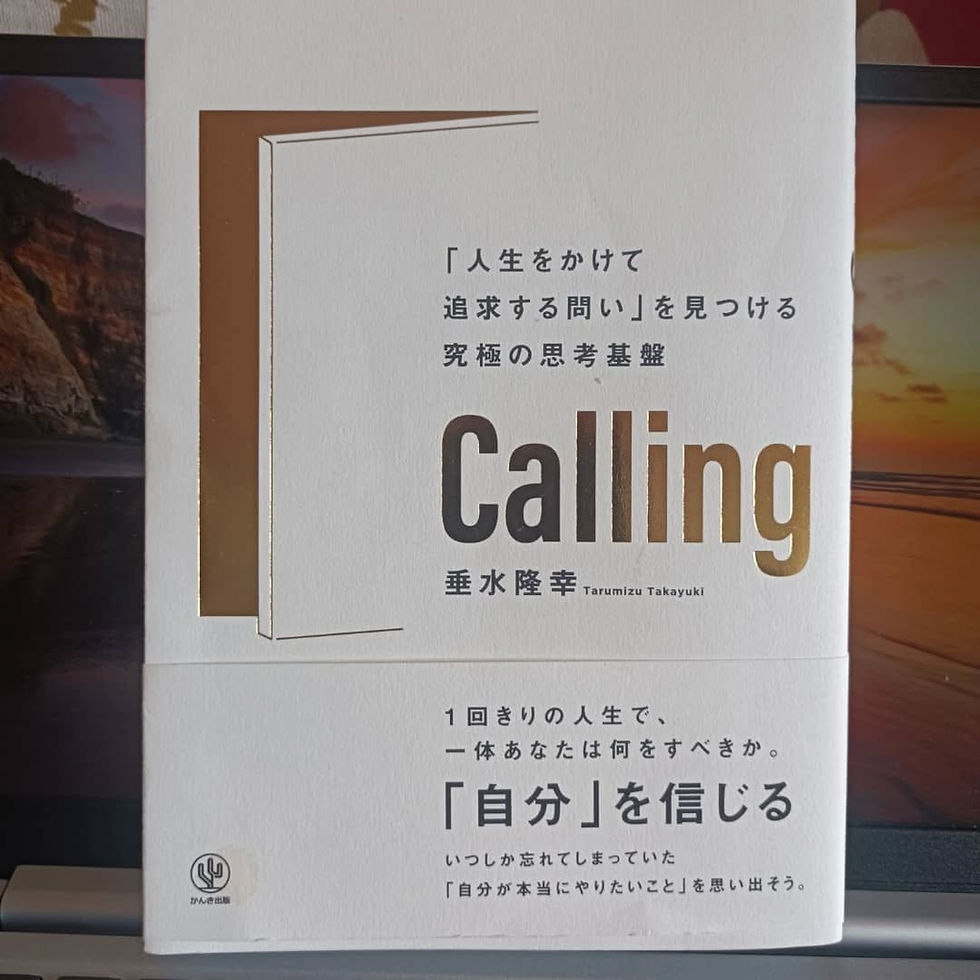
今回も心に留まったフレーズを残そうと思う。
自己実現とは、自分の持つ可能性を最大限に活かし、独自の価値観や情熱に忠実に行動すること。(p33)
そのために、「Calling」が重要になってくる。
純粋で個人的な喜びや充実感が、社会的な価値の創造へとつながっていく。
個人の独自の視点が、新しい問題解決の可能性を拓く。
主観的な情熱が、客観的な成果へと結実していく。
コーリングとは、個人の内面と社会的現実との対話を促す力。
主観と客観を橋渡しするのが、コーリングの本質である。(p44)
「他者との深い関係性」の中でコーリングを磨き、表現していく。
いくら内なる声が強くとも、孤立した状態では行動や影響力が限られてしまう。(p61)
コーリングを、単に内なる声と考えるだけではなく、内と外を繋ぐ声と理解することで、受け取り方に広がりを生む。
コーリングに動かされている活動は、「やっている行為そのもの」に強い使命感や意味を見出せます。(P87)
コーリングは主観(個人)と客観(社会)を橋渡しする力があるだけではなく、目的と手段を統一する力でもある。
違和感は単なる不快感ではなく、私たちのコーリングが発する重要なシグナルを含んでいる。
違和感の背後にある自分の価値観は何か。
なぜ自分はその状況を受け入れがたいと感じるのか。
その抵抗感は何を守ろうとしているのか。
自分が理想とする状態と、目の前の現実とのギャップはどこにあるのか。(P124)
違和感の正体について、自分が答えを知っている。
直感的に知っていることは理解しているのだ。
しかし、直感的に知っている答えを直視する力があるか。
違和感や抵抗感に向き合うには「力」が必要だと思う。
その「力」をどう養うか。
「自分には力がないのだから、難しいことだ」とあきらめることは簡単だ。
しかし、本当に力はないのだろうか。
それこそ、「本当は力がある」という事実にこそ、恐れを感じているのかもしれない。
コーリングとは、外部の正解に頼らず、内から湧き上がる声に耳を傾け、それを他者との関係性の中で育む道標。
物語。
私たちは自分自身や人生を理解するために、自分にまつわるある種の「物語」を無意識に作り上げます。
その物語が私たちの行動を無意識のうちに制約していることが多い。
新しい物語を相対化したうえで、新しい物語へと積極的に置き換えていく試みが「物語の再構築」です。(P195)
少し悩んでいたことがある。
まさにこのテーマで、自分の人生を物語として理解することで、大きな力を獲得できる。
それは、自分の行為が、何のためにあるのかを理解できるからだ。
ど真ん中名刺は、まさに自分の物語を理解して、その中から今の自分に必要な要素を抽出して作るプログラムだ。
そういう意味で、「エディットワーク(物語を編集する作業)」と名付けている。
しかし、物語を内面化する代償として、物語の外の世界に関心を持ちづらくなる。
違和感を感じたとしても、それに向き合うことを意識的に辞めることになる。
「この違和感は、自分の物語の外にあることだから、考える必要はない」と。
物語の内面化が強化されるほど、物語の結末への道は明確になったとしても、その物語を一緒に共有する仲間が固定化される、自分の予想を超える冒険への挑戦ができなくなるなど、創造性が減る。
自分の物語の世界・共同幻想のハコの中では、仲間とのつながりは強化されるだろうし、成果は出やすいだろうし、ハコの世界の中では評価もあがるだろう。
しかし、それが目指す世界だっただろうか。
物語の結末へ効率よく目指すこと自体が間違いの可能性がある。
結末自体不要な可能性だってある。
循環する世界観だ。
では、物語理解を手放すことが正解なんだろうか。
ここが、どうも長年腹落ちできていなかった。
本書にある「物語の再構築」。
いつでも、自分の物語を書き換える余白をもっておく。
それこそ「自由」なのかもしれない。
道標
軌跡
発見
試練
挑戦
鍛錬
拡張
帰還




コメント